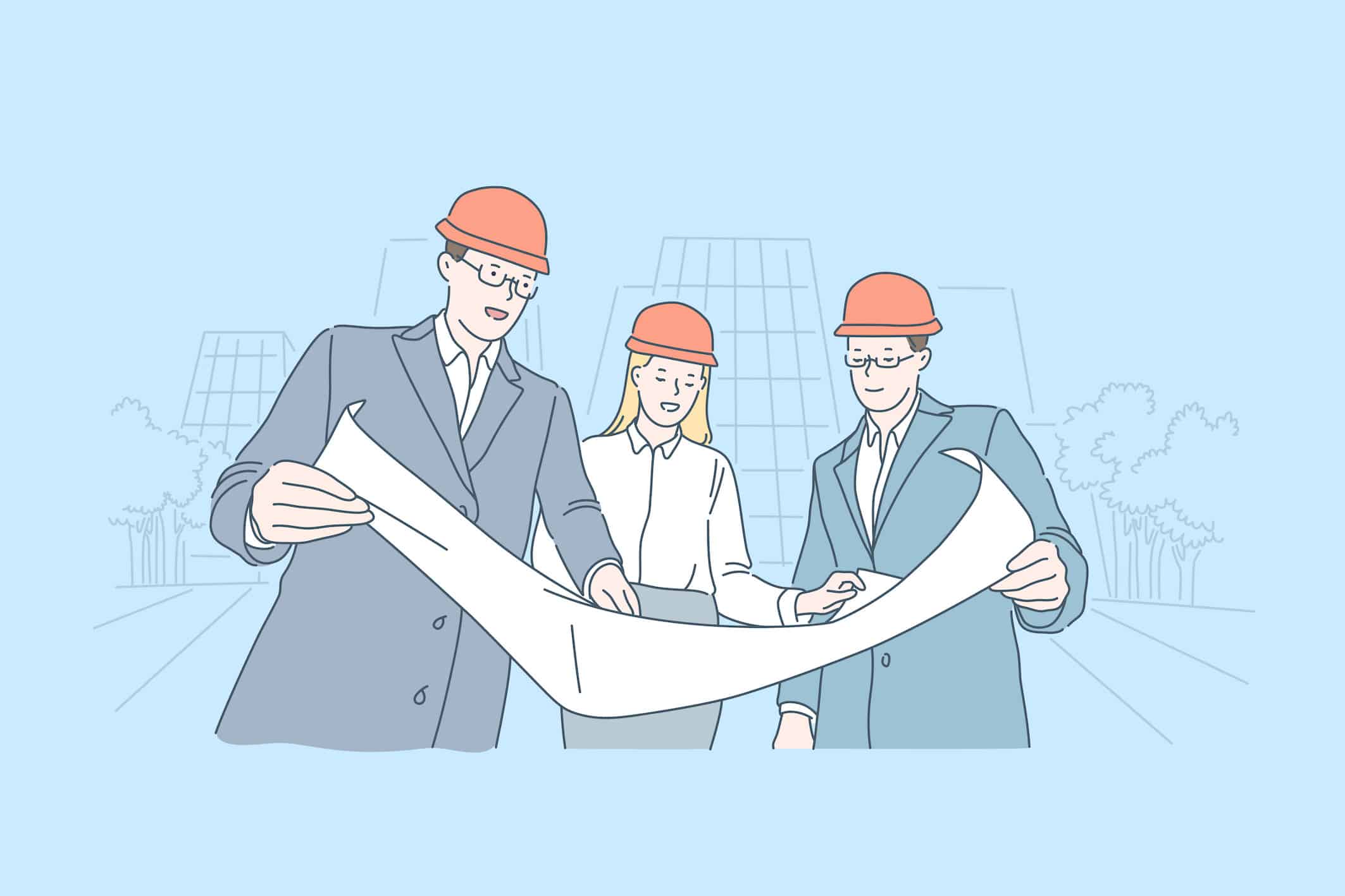作業手順書とは、業務を構成する各作業の手順や注意事項を示す文書です。業務を円滑に進めるために整備され、企業や従業員にとって重要な役割を担っています。
作業手順書は多くの企業で整備されていますが、業種によって求められる内容や作成手順には若干の違いがあります。
今回は、製造業と建設業に焦点を当て、それぞれの業種における作業手順書についてご説明します。
製造業の作業手順書の目的とは
まずは、製造業における作業手順書について見ていきましょう。
製造業における作業手順書は、製品や生産に直接影響を与える重要な文書で、主に以下の目的で整備されています。
目的1: 製品・製造の品質維持
製造業における作業手順書の主な目的の一つは、「製品や製造の品質を維持すること」です。
製造業では、製品の品質にバラつきがあってはなりません。また、製造技術や工程の違いも製品や製造効率に影響を与えます。しかし、作業手順書が整備・運用されていれば、すべての作業者が作業手順書に従って製造作業を行うため、製品の品質や製造技術、工程の差異が生じにくくなります。
作業者が誰であっても、同じ品質、技術、時間で作業を行えるようになることが、作業手順書のメリットであり目的です。
目的2: 製造業務の効率化
作業手順書は、製造業務の効率化にも役立ちます。
なぜなら、作業手順書は作成や運用の過程で無駄な工程を洗い出し、効率的な作業手順を完成させやすくするからです。無駄のない作業手順書に沿って全ての作業員が作業することで、業務における無駄がなくなり、製造業務の効率アップが期待できます。ただし、無駄な作業が含まれていたり、必要な作業が抜けていたりすると、作業手順書の質が悪くなり、逆に業務効率が低下する恐れがあります。
目的3: ノウハウの蓄積
作業手順書の目的は、目の前の業務に関することだけに留まりません。作業手順書に書かれるノウハウを蓄積し、会社の財産として管理・伝承していくことも、作業手順書を作成する目的の一つです。作業手順書に記載される内容は、多くの従業員が培ってきた経験や知識をまとめた、ノウハウという名の財産です。
ノウハウは簡単に手に入るものではないため、それを情報として管理・利用していくことは、企業経営において大きなメリットとなります。ただし、有効なノウハウを蓄積していくためには、作業手順書を作成するだけでなく、その後も内容を精査し、随時アップデートを続けていく必要があります。
製造業の作業手順書作成のポイント
次に、製造業における作業手順書作成のポイントを4つご紹介します。作業手順書を作成する際には、以下のポイントに加え、実際に作業手順書を読む作業者の視点を意識するようにしましょう。
1. 目的や現状の問題点を明確化する
作業手順書作成にあたっては、まず作業手順書を作成する目的と現状の問題点を明確にすることが求められます。目的に合致した内容であり、かつ問題を解決できる内容でなければ、作業手順書を整備する意味がなくなってしまいます。
まずは目的や問題を把握し、作業手順書によってそれらが解決可能か、どのような内容にするべきかなど、基本的なコンセプトを構築しましょう。その後の作業は、このコンセプトに基づいて進めていきます。
2. 誰が見ても理解できる内容にする
作業手順書を実際に利用するのは、現場で働く作業員たちです。作業員にはさまざまな年齢や背景を持つ人が含まれると予想されます。そのため、作業手順書は誰が見ても理解できる内容である必要があります。専門用語や難しい言い回しを避け、簡潔でわかりやすい言葉を使用することが重要です。
また、必要に応じて専門用語の説明や非常時の対応を詳しく記載することで、作業手順書の汎用性を高めることができます。
3. 誰もが利用しやすい運用体制を取る
作業手順書作成においては、運用後の利用しやすさも重視する必要があります。どれほど内容が優れていても、利用しづらければ作業手順書は活用されなくなってしまいます。作業手順書の運用には、専用ツールを用いるなどし、実際に利用する作業者が必要な時にすぐ利用できる体制を整えましょう。
また、作業手順書を運用するツールは多くリリースされていますが、操作性はツールごとに異なります。ツール導入の際には、試用期間を活用して、自社に最適なツールを選ぶことが重要です。
4. 運用と改善を続けていく
作業手順書は、一度作成して終わりではなく、運用しながら必要に応じて改善を続けていくことが求められます。これにより、現状に最適な作業手順書を常に維持することが可能になります。作業手順書が完成したら、まずは小規模な試運用を行い、必要に応じて改善を加えます。
その後は本格運用に移り、担当者が継続的に管理を行うことになります。そのため、作業手順書作成にあたっては、あらかじめ運用担当者を選定しておくことも必要です。
建設業の作業手順書の目的とは
次に、建設業における作業手順書について見ていきましょう。建設業における作業手順書は、現場での作業の指針として作成されています。建設業という業種では「作業員の安全性」と「建物を利用する人の安全性」が求められるため、建設作業の標準となる作業手順書の内容は、人命にも直結すると言えるでしょう。建設業における作業手順書では、以下の点が特に重要です。
- 法令や社内基準と矛盾しない内容にすること
- 見やすく、読みやすく、理解しやすいこと(写真や図表を活用した視覚的表現を取り入れる)
- 作業を担う全員が実行できる内容であること
- 過去に起こった事故・災害の事例に基づく反省や対策が含まれていること
法令や過去の事例を反映し、誰もが簡単に理解できる内容にすることが、建設業における作業手順書には求められます。
建設業の作業手順書の基本様式
建設業の作業手順書には、以下のような基本的な項目を含める必要があります。
- 作業手順書作成日および改定日
- 作業名
- 作業内容
- 作業人員
- 必要な機械・材料
- 過去に起こった事故や災害の事例
- 準備・本作業・後片付けの作業区分
- 作業手順
- 作業の急所
- 予想される災害と危険性・有害性の調査
- 予想される災害への低減措置と低減措置後の危険性・有害性の調査
- 低減対策の実施責任者記入欄
(参考: 一般財団法人中小建設業特別教育協会HP https://www.tokubetu.or.jp/text_shokuan/part4/text_shokuan4-2.html)
予想される災害の危険性や有害性、そしてその低減措置に関する項目は、作業員や建物を利用する人の安全性に深く関わるため、特に綿密な調査の上で作成されるべきです。
建設業における作業手順書は、上記の基本項目に加え、必要に応じて追加項目を設定して完成されます。
建設業の作業手順書作成手順
ここからは、建設業における作業手順書の作成手順について見ていきましょう。
手順1: 単位作業の洗い出し
建設業の作業は、比較的大きな「まとまり作業」と、それを分解した「構成作業」、さらにそれを分解した「単位作業」から成り立ちます。
たとえば、「足場の組立解体作業」を「まとまり作業」とすれば、「足場の組立作業」「足場の解体作業」などが「構成作業」、そして「準備」「搬入」「足場1層目の組立」などが「単位作業」に該当します。作業手順書を作成する際は、まずこの細かな「単位作業」を洗い出すことから始めます。
手順2: 単位作業の分解
次に、手順1で洗い出した単位作業をさらに分解し、単位作業を行うための具体的な手順を作成します。たとえば、「足場一層目の組立」という単位作業を分解すると、「使用工具の点検」「立ち入り禁止区域の設定」など、さらに細かな手順が導き出されます。
この作業については、現場で実際に行われている作業と差異がないように、現場の職人や責任者と確認を行うことが重要です。
手順3: 手順の追加、削除、並び替え、区分
手順2で導き出した手順について、必要に応じて追加や削除、並び替えを行い、作業実施において最適な手順を決定します。決定された手順は、「準備作業」「本作業」「後片付け作業」の3つに区分します。
手順4: 急所の記入
安全面・生産面・品質面の観点から、各手順ごとの急所(重要点)を検討し、記載します。急所欄は作業の安全性や品質を左右する重要なポイントであるため、明確な表現を心がけましょう。具体的であり、副詞的表現(「〜して」など)を用いることが推奨されます。
手順5: 危険性・有害性の評価、対策
過去の事例をもとに作業の危険性や有害性を洗い出して評価し、必要に応じて低減措置を実施し、その結果を反映させて作業手順書を修正します。
手順6: 事故・災害事例の記入
過去に発生した事故や災害の事例を教訓として記載し、再発防止に役立てます。
作業手順書作成時のチェックポイント
建設業における作業手順書を作成する際には、以下の5つのチェックポイントについて検討を行ってください。
| ①単純化できるかどうか | 手順や設備の変更によって、作業を単純化できる余地はないか |
| ②順番に改善の余地はないか | 手順の順番は円滑かより効率化できる順番はないか |
| ③問題のある動作はないか | 準備に問題はないか必要なものが必要な場所に用意されているか |
| ④無理のある動作はないか | 作業員に無理をさせる内容になっていないか作業を妨げる条件はないか |
| ⑤作業分担に問題はないか | 作業分担の漏れや不備はないか異常時の対応も問題なく分担されているか |
特に手順の追加や削除、並べ替え時には、上記のポイントを踏まえて作業を行いましょう。
まとめ
作業手順書は、どの業種においても効率性や安全性の向上に役立つ重要なツールです。しかし、その作成手順やポイントは、すべての業種で共通というわけではありません。特に建設業では、業界特有の手順やポイントに基づいて作業手順書が作成されます。質の高い作業手順書を作成するためには、業種の特性に合った方法や内容の選択が必要です。
また、ノウハウが蓄積された作業手順書を従業員全員が利用し、業務に生かしていくためには、情報共有ツールの活用が有効です。これらのツールを用いることで、作業手順書はより使いやすくなり、新しい情報も簡単に共有できるようになります。業種に関わらず、今後の企業経営において、情報共有ツールの導入はますます重要性を増すと考えられます。
作業手順書/マニュアルならトースターチーム
トースターチームは、業務手順の学習と生産性を高め、即戦力人材の育成と定着を実現するマニュアル作成ツールです。
ステップ構造を取り入れたエディタで、統一されたフォーマットの手順書・マニュアルを誰でも簡単に作成することができます。属人化している業務をマニュアル化することで、他のメンバーがPC/スマホ/タブレットでいつでも・どこでも閲覧・確認できる環境を構築できます。これにより、業務の再現性と生産性を大幅に向上させることが可能です。
現在、14日間の無料トライアルを実施中ですので、ぜひお試しください。