法人営業に関わっている方であればBANTの重要性が理解出来ていると思いますが、細かな知識が不足していることもあります。
BANTは商談や成約に欠かせないものであり、十分な知識を得た上で活用するものなのです。この記事ではBANTについての情報と、活用のコツや注意点を説明しましょう。
BANTについての理解を深めたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
BANTとは

BANTとはBudget(予算)、Authority(決裁者・決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)の4つの頭文字を合わせた言葉です。
この項目をヒアリングすることが、商談を進めたり、成約の確度を評価したりする上でのひとつの指標となるのです。
ここからは、それぞれの項目について説明しましょう。
Budget(予算)
顧客によって、予算を確保できている場合と、そうでない場合があります。なぜなら、顧客は新しいサービスや商品を購入する際には、先方の提案を受けた後に予算取りを行うためです。
そのため予算の有無だけでリードの確度を判断してしまうことは避けましょう。まだ予算が確保できていないとしても「良いものがあれば予算は用意出来る」という顧客も一定数存在します。
また、これから予算を検討してもらう場合には、どのようなプロセスで予算を確保するのかを理解しておくといいでしょう。
Authority(決裁者・決裁権)
法人営業では商談の相手が決裁権を持っていることは少なく、社内稟議などが通った上での成約となるでしょう。商談時には、最終的な意思決定をする決裁者が誰であるかを押さえておく必要があります。
目の前の相手が営業案件の決裁権を持っているかを把握し、違うようであれば決裁権のある相手に直接アプローチした方が成約率の向上につながるためです。
Needs(必要性)
顧客に自社の商品やサービスが必要とされているかを判断します。担当者の個人的な意見ではなく顧客の企業全体を見て、自社の提案が顧客にマッチしているかを確認してください。
自社の商品やサービスを必要と感じていない相手に提案を続けても、良い方向に話を進めることは難しいでしょう。
Timeframe(導入時期)
自社の提案に必要性を感じている企業だとしても、導入時期が決まっていない場合、または未定の場合は具体的な商談が進められません。
導入時期が分かっていれば、案件の管理もしやすくなり、顧客の導入段階に合わせたアプローチが行えるでしょう。
BANTを活用する際のコツ

BANTの基本的な内容をお伝えいたしましたので、BANTを活用する際のコツを理解しましょう。
コツを理解していれば、すぐにBANTが使いこなせるようになります。
コツ1 予算は最初に確認する
顧客が予算を確保しているのであれば、最初に予算を確認して予算規模に合わせた提案が出来るようにしましょう。
「100万円の提案」と「1,000万円の提案」では、提案内容はもちろんそのために用意するべきアプローチも全く違うものになります。予算規模を把握することで、顧客に最適な提案が出来るようになるのです。
しかし多くの場合は、商談段階では明確な予算が確保されていません。顧客には金額によって提案内容が変わることを説明し、できるだけ予算感だけでも把握するようにしてください。
コツ2 さりげなく決裁ルートを把握する
決裁ルートの確認は重要ですが、担当者にいきなり決裁ルートを聞いてはいけません。
まだ信頼関係が築けていない相手から突然決裁ルートを聞かれた担当者は、自分を飛ばして決裁者へ直接アプローチされることを恐れ、口を閉ざしてしまうことがあるためです。
決裁ルートを単刀直入に聞き出すのではなく、稟議手順を聞く流れに含めて確認するなど、さりげなく聴取するようにしましょう。
また、稟議が通るまでに必要なステップも聞いておきます。例えば「上司に説明すれば良い」「上司だけでなく役員への説明が必要」「定例会議で提案し承認される必要がある」など、決裁ルートと必要なステップは会社によって異なります。
コツ3 顧客のウォンツからニーズを掘り起こす
顧客が持つニーズと似た言葉として、ウォンツがあります。
ニーズは目的であり抽象的なもので、ウォンツは具体的な手段だと考えれば良いでしょう。具体例で説明すると「社内で情報共有をスムーズに行いたい」=ニーズ、「情報共有ツールを導入したい」=ウォンツになります。
商談の中で顧客は常にウォンツ寄りの発言が多くなるため、そのウォンツに隠されたニーズは何なのかを掘り起こすようにしてください。
コツ4 スケジュールを自分から提案する
顧客側で商品やサービスの導入スケジュールがまだ決まっていない場合には、自社から仮設定のスケジュールを提案するという手段もあります。
もちろんこのスケジュールは正式なものになはりませんが、顧客側で商品やサービス導入のためのスケジュールがイメージしやすくなるのです。
スケジュールを曖昧にしないことで、成約後に顧客から無理なスケジュールを希望されることもなくなるでしょう。
BANTを活用する際の注意点
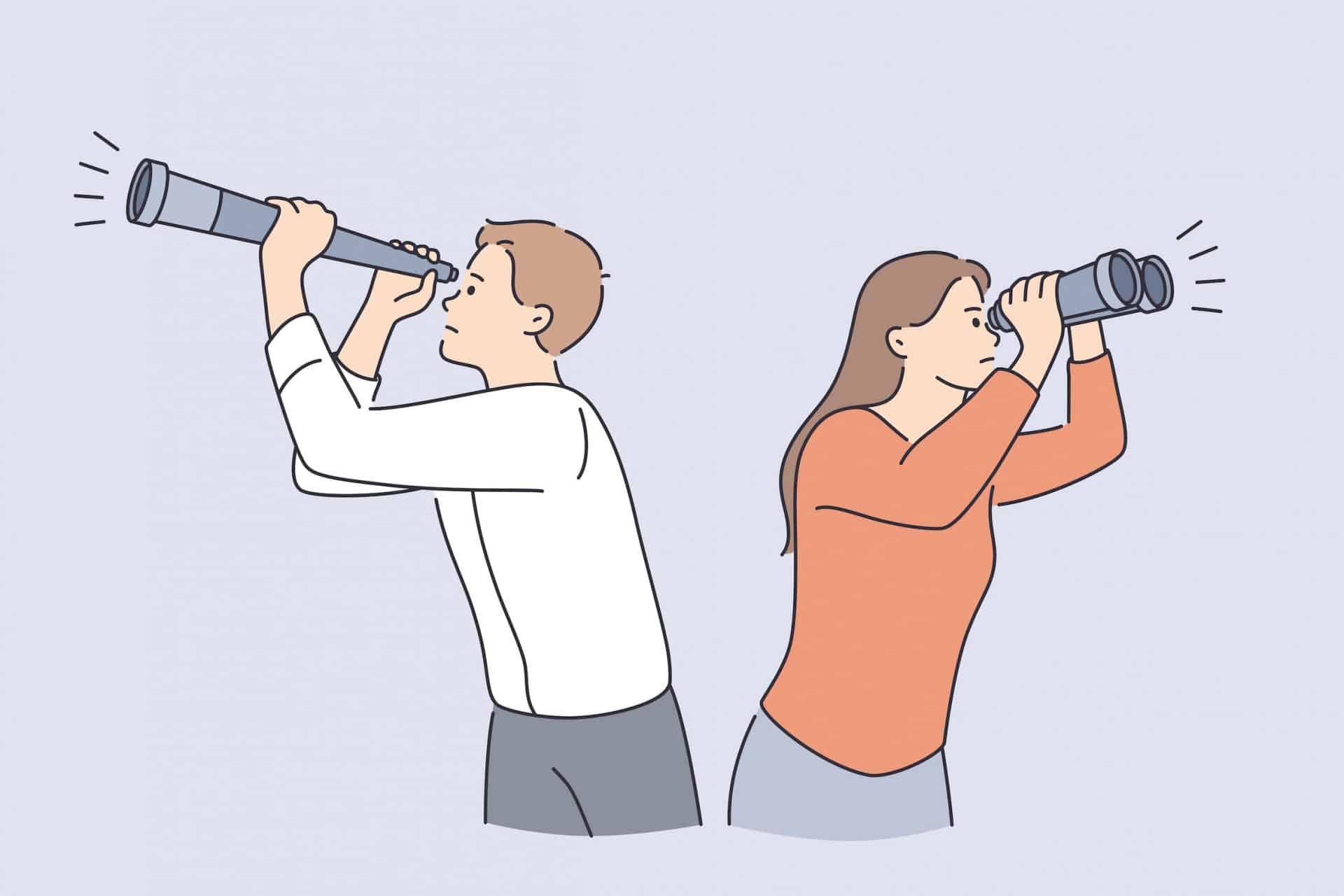
BANTを活用するためには、知っておくべき注意点があります。ここでは、その注意点を紹介しましょう。
注意点1 その場の空気感に敏感になる
BANTの情報を集めようと意識しすぎると、商談が雑になってしまうことがあります。
商談ではその場の空気感を敏感に察知し、顧客との信頼関係を築きながらBANTの収集に取り組むようにしましょう。
商談はお互いの信頼関係を構築するためにあります。情報だけが手に入っても、商談が失敗に終わるのでは意味がありません。
注意点2 BANTはアンケートではなくヒアリングで活用する
アンケート調査などで得た情報は、ヒアリングで得る情報とは全く違った内容になることが多いです。
例えば「自社製品の購入予定はありますか?」に対し、アンケートには「いいえ」と答えているものの、ヒアリングでは別の答えが出てくることもあるのです。
そのためBANTは営業が直接ヒアリングしたものでなければ、信憑性が低い情報になってしまうということです。アンケートで得た情報は参考程度に留めておくと良いでしょう。
注意点3 日本企業ならではの特性を理解する
BANTは欧米で生まれた概念であり、日本企業の特性に合わない場合もあります。
特に規模が大きな日本企業では、決裁者が分かりにくい、予算権限は別の担当者になるなど複雑なシステムが構築されており、BANTによって営業マンが内情を理解することが難しいのです。
BANT情報を無理に全て聞き出そうとせず、企業の特性に合わせた臨機応変な対応が出来るようにしましょう。
注意点4 BANTに頼りすぎない
BANTによって十分な情報が手に入っていたとしても、想定外のトラブルによって予算やスケジュールが変更されることは珍しくありません。
BANTはあくまで顧客情報を把握するための手段であり、その情報は状況によって変更される可能性があるものだと理解しておきましょう。
まとめ
BANTについての基本的な情報と活用のコツ、注意点を紹介いたしました。BANTは成約率を上げるために欠かせないものであり、BANTを理解して商談を進めれば、顧客に最適な提案が出来るようになるでしょう。
また、効率良く営業活動を進めるためには、営業ツールやセールスイネーブルメントツールの導入も必要です。
営業資料の中で顧客がどのページを閲覧したか分かるツールもあり、活用すれば顧客の温度感や求める機能などが事前に分かり、商談はよりスムーズに進められるでしょう。
自社に最適な営業スタイルを見つけ、効率良く成約率を向上させていきましょう。



