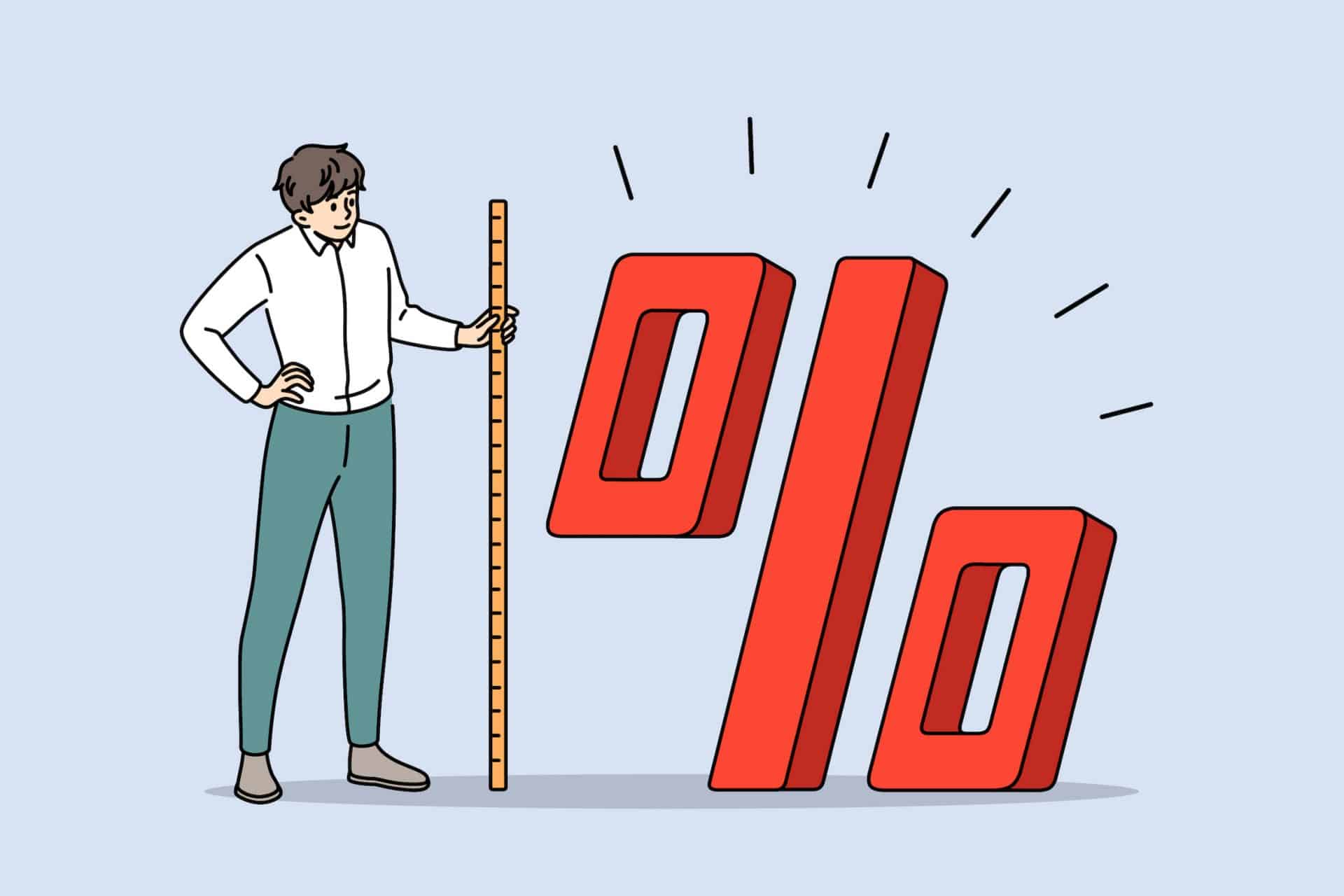BtoB企業が顧客に対して営業やマーケティング活動を行うにあたっては、顧客の購買プロセスを正確に理解しておくことが大切です。顧客の購買プロセスを理解しておけば、企業は最適なアプローチを実施することができ、営業活動はより効果的で効率的なものになります。
では、 BtoB分野において、顧客の購買プロセスを理解するには、どうしたらいいのでしょうか。
今回は、顧客の購買プロセスを理解することの重要性や理解するための方法、BtoBとBtoCの購買プロセスの違いなどについてご紹介しますので、ご参考になさってください。
購買プロセスとは
購買プロセスとは、顧客が自身の購買ニーズに気づいてから実際に商品を購入するまでのプロセスを指す言葉です。
人間は物を購入するにあたって、複数のプロセスを踏みます。衝動買いなどの例外もありますが、「現状の問題やニーズを認識して製品を探し、製品を比較検討して購買に至る」というような流れが、人間が物を買う一般的な流れでしょう。
この購買プロセスは、企業の営業活動やマーケティング活動に大きく影響します。そのため、購買プロセスへの理解は、企業にとっての重要な課題のひとつになっています。
購買プロセスを理解することが重要な理由

前述の通り、購買プロセスを理解することは、商品やサービスを顧客に販売する企業にとって重要なポイントです。各プロセスに適したアプローチを行うことで、企業は顧客を効率的に次のプロセスへと進めることができます。
近年では、インターネットの普及や市場の変化などによって、顧客が商品やサービスの価格、品質をより重視し、比較するようになりました。これにより、以前よりも購買プロセスは複雑になってきています。
中でもBtoBの購買プロセスは複雑で、プロセス上の登場人物も多数います。toB向けの商品やサービスを扱っている企業が顧客に選ばれるためには、顧客側の購買プロセスと登場人物を把握する必要があります。
「誰がどのような行動をすればプロセスを進められるのか」を理解しておけば、顧客の購買プロセスに応じたアプローチやプロモーション、サービス開発を行うことができます。これにより、購買プロセスの円滑な進行や成約を目指すことが可能になります。
「BtoBの購買プロセス」と「BtoCの購買プロセス」の違い
「BtoBの購買プロセス」と「BtoCの購買プロセス」には違いがあります。それぞれの購買プロセスは、「ASICA」と「AIDMA」、「AISAS」という購買行動モデルで表すことができます。
BtoBの購買行動モデル「ASICA」
「ASICA」は、一般社団法人日本BtoB広告協会副会長を務めた河内英司さんによって提唱された、BtoBにおける購買行動モデルです。「ASICA」では、BtoBにおける購買行動モデルを以下の5段階に分けます。
①Assignment(課題):顧客企業が抱える課題を洗い出し、認識してもらう
②Solution(解決):課題の解決策を提案する
③Inspection(検証):提案された解決策の検証が行われる
④Consent(承認):決裁者による承認
⑤Action(行動):購入
BtoBの購買プロセスはこのような流れで進み、成約を勝ち取るために、営業担当者は③の段階の検証にあたって自社商品の優位性を示したり、④の段階の承認プロセスで決裁者向けのプレゼンを新たに行ったりする必要があります。
それぞれのプロセスにはある程度の時間もかかり、顧客企業は担当者やその上司、決裁者など多くの登場人物の承認を経て、購買プロセスを進めていきます。
BtoCの購買行動モデル「AIDMA」「AISAS」
「AIDMA」は、アメリカのサミュエル・ローランド・ホール氏によって提唱された BtoCにおける購買行動モデルです。「AIDMA」では、顧客の購買プロセスを以下の5段階で表しました。
①Attention(注目):製品・サービスの存在を知る
②Interest(興味):製品・サービスに興味を持つ
③Desire(欲求):製品・サービスが欲しくなる
④Memory(記憶):製品・サービスを記憶する
⑤Action(行動):製品・サービスを購入する
インターネットを利用する顧客の場合は、「AIDMA」と異なる購買プロセスを踏みます。それを購買行動モデルにしたものが、「AISAS」です。「AISAS」は、インターネットを利用する顧客の購買プロセスを以下の5段階で表現しています。
①Attention(注目):製品・サービスの存在を知る
②Interest(興味):製品・サービスに興味を持つ
③Search(検索):製品・サービスを検索する
④Action(行動):製品・サービスを購入する
⑤Share(共有):購入した製品・サービスをインターネットで共有する
このように、 BtoBとBtoCの購買プロセスは大きく異なり、その違いは既存の購買行動モデルで表されています。
BtoBの購買プロセスを理解するための4ステップ

BtoBにおいて、具体的な顧客の購買プロセスを理解するにはどうすればいいのでしょうか。
ここからは、購買プロセスを理解するための4つのステップをご紹介します。
STEP1 稟議が承認されるまでのフローを把握
顧客企業の購買プロセスを理解するためには、まず顧客企業で稟議が承認されるまでのフローを把握することが必要です。「誰がどの権限を持ち、どんな流れで稟議が承認されるのか」を把握しておくことで、顧客企業の購買プロセスは明確になってきます。
多くの場合、稟議が承認されるまでのフローや意思決定者、権限の範囲などは公式に定められています。
「もしこのプロジェクトを実行するなら、次は稟議の申請ですか?」などと、会話の中でさりげなくフローの情報を聞き出していきましょう。
STEP2 最終意思決定者を把握
稟議承認のフローにおける最終意思決定者を把握しておくことも、顧客企業の購買プロセスを理解するために重要です。最終意思決定者とは、「この人の意思で稟議の承認または拒否が決まる」という権限を持った人のことです。
金額や内容によって、最終意思決定者は異なります。「この内容のプロジェクトであれば、本部長承認でしょうか?」などの質問で、最終意思決定者を把握していきます。
STEP3 各関与者の行動プロセスを把握
稟議承認フローと最終意思決定者が把握できたら、稟議承認に関わる人物の行動プロセスを把握していきます。稟議承認に関わる人物の行動プロセスとは、「担当者が課長に案件の説明をする」「課長が会議で部長に説明して承認を得る」「重要度の高い案件は部長が本部長に説明し承認を得る」など、稟議フローにおける関係者とその行動のことです。
稟議フローの中で「どのフローで誰が何をするか」ということを把握し、営業担当者は顧客の行動プロセスに合った方法で稟議フローをサポートする必要があります。
STEP4 案件推進者を把握
案件推進者とは、顧客側で「このプロジェクトを推進したい」という強い気持ちを持っている人のことです。案件推進者が権限を持っているとは限りませんが、権限がなくても、案件推進者の積極的な行動によって稟議が通りやすくなる可能性があります。
案件推進者とは、パートナーとして活動できるよう、信頼関係の構築を目指しましょう。
まとめ
顧客の購買プロセスを知ることは、 BtoB企業にとって非常に重要です。購買プロセスを把握し各プロセスに合ったアクションを行うことで、成約率向上が期待できます。
そのためには、購買プロセスをさりげなく聞き出すための営業トークを練習しておいた方がいいでしょう。
また、成約率向上には、セールスイネーブルメントツールの活用も効果的です。
営業に関する施策をトータル管理し、その成果を可視化するセールスイネーブルメントツールがあれば、各成果の貢献度が一目でわかり、うまくPCDAサイクルを回すことができます。営業施策を継続的に改善していけば、営業活動は効率化し、成約率も上がるでしょう。また、ツール上での情報共有機能によって、顧客の購買プロセスや進捗の社内共有がしやすくなれば、組織として顧客に対し一貫した対応を行うこともできます。営業活動にはツールをうまく活用し、効率化を図りましょう。