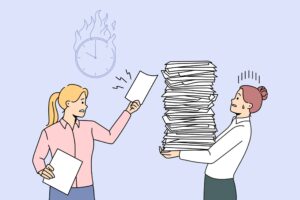ビジネスにおいて、情報共有は重要な意味を持つ経営手段のひとつです。情報を共有することによるメリットは大きく、現在では多くの企業が情報共有に重きを置いています。
そして近年では、このような流れに伴い、高性能な情報共有ツールがリリースされ、企業に採用されるようになりました。
では、この情報共有ツールにはどんな魅力があるのでしょうか。
そこで今回は、情報共有ツールについて、メリット・デメリットや選び方のポイント、具体的なツール例など詳しくご紹介しましょう。
情報共有ツールとは
情報共有ツールとは、名前の通り情報共有を行うためのコンピューターツールのことです。
業務に関する既存の情報を従業員が入手できたり、従業員同士の情報交換ができたり、またツール内で共同作業ができたりと、情報を企業内および従業員間で活用するための機能が、情報共有ツールには搭載されています。
情報活用は、企業活動にとって多くのメリットをもたらす有益なものです。そのため、近年情報活用の仕方は経営手段のひとつとして注目されており、さまざまな情報共有ツールがリリースされてきました。多様な情報共有ツールは、それぞれが特徴的な機能や使用方法を搭載し、企業の情報活用に用いられています。
情報共有ツール導入により期待できる効果
まずは、企業内で情報共有ツールを用い、情報を共有することにより期待できる効果についてご紹介しましょう。ツール利用による情報共有に期待できる効果は複数ありますが、中でも大きなものとしては、「業務効率化」と「ノウハウの蓄積」が挙げられます。
業務効率化
情報共有は以下のような理由により、業務効率化に繋がります。
- 業務手順の情報共有により業務の均質化が可能になる
- 専門知識の共有により業務の属人化を防止できる
- 勝ちパターンの情報共有により全体の成績がアップする
業務の質にばらつきがあったり、業務そのものが属人化してしまったりすれば、その業務は効率的に進まず、滞る恐れがあります。しかしこれは必要な情報を共有することで解決することが可能です。
また、有益な情報を共有すれば、知識を持った従業員が増え、業務の成功率は向上します。
このような情報共有による業務効率化は、企業にとっての利益を生み、企業価値の上昇にも繋がるため、情報共有の大きな目的として据えられています。
ノウハウの蓄積
ビジネスに関するノウハウは、個人の経験によって培われていきます。しかし、このノウハウを情報として共有しなければ、個人が培ったノウハウは個人だけのものとなり、十分に生かすことができません。ノウハウを持った人が企業から転職してしまえば、そのノウハウ自体も企業から流出してしまいます。
そこで重要視されているのが、情報共有によるノウハウの蓄積です。個人の持っているノウハウを企業の情報として共有し蓄積していくことで、企業は経験に基づいた重要な情報を保持することができます。
このような情報は企業にとっての財産となるため、ノウハウの蓄積は情報共有における重大な目的となっています。
ツールを使うメリット・デメリット
情報共有には、専用の情報共有ツールの使用が便利です。現在ではさまざまな情報共有ツールが開発されており、高い機能性で企業のニーズに応えています。
そこでここでは、情報共有ツールを使用するメリットとともに、頭に入れておきたいデメリットについてもご紹介しましょう。
ツールを使うメリット
効果的な情報共有システム導入が簡単に行える
各情報共有ツールには、既に備わっている機能やテンプレートがあります。そのため、一からシステムを構築する必要がなく、汎用性の高い機能やテンプレートを用いて、早く簡単に情報共有システムを導入することが可能です。
ただし、自社の課題解決にマッチするツールを選択する必要があるため、事前の課題洗い出しとツールの機能確認は必須でしょう。
誰もが必要な時に必要な情報を引き出せる
多くの情報共有ツールは、パソコンやタブレット、スマートフォンに対応し、企業内の人間であればいつでもどこでも情報を共有できるようになっています。個々の従業員が必要な時に必要な情報を引き出せ、効率的な業務遂行が叶うのは、大きなメリットでしょう。
このような情報が手に入れやすいツールがあることにより、従業員はスムーズに業務を進められ、企業としての従業員満足度も向上します。
ノウハウの蓄積がしやすい
情報共有ツールは、ノウハウの蓄積がしやすいのも特徴です。個人のノウハウを情報としてツール内に入力していけば、ツールが情報ボックスとなり、培われたノウハウを企業のものとして蓄積していくことができます。そして、ツールを利用することにより、個人のノウハウを企業内の従業員が活用することが可能になります。
ただし、ノウハウを情報に変換し入力するのは簡単な作業ではないため、なるべく入力しやすく活用しやすいツールを選ぶことが大切です。
ツールを使うデメリット
直接のコミュニケーションが減る
情報共有ツールがあれば、人に聞かずに情報を得ることができます。また、多くのツールにはチャットやメールなどのコミュニケーション機能が搭載されているため、あらゆる連絡がツールを使うことで事足りてしまいます。
これによるデメリットとして挙げられるのが、従業員同士の直接のコミュニケーションが減ってしまうことです。業務によっては、直接コミュニケーションを取ることによって、新しいアイディアが出たり、ニュアンスが伝わったりするものもあるでしょう。また、直接のコミュニケーションでは団結力や協調性も培われます。
情報共有ツールと直接的コミュニケーションの両方のメリットを得るには、場面によった使い分けが必要です。
こまめな情報整理が必要
共有する情報は常に最新の情報にアップデートしておく必要があるため、こまめな情報整理が必須です。また、ノウハウを持った個々の従業員は、情報を受け取る側としてだけではなく、情報を発信する側としてもツールを活用しなければなりません。
このように、情報共有ツールは導入しっぱなしでは生かされず、企業全体で常に情報整理を行なっていく必要があります。この管理労力が必要だという点は、ひとつのデメリットだと言えるでしょう。
情報共有ツールの代表的な機能
情報共有ツールには、各ツールによって多様な機能が搭載されています。ここではその中から、多くの情報共有ツールに搭載されている代表的な機能をご紹介しましょう。
1.マニュアル機能
マニュアルとは、業務のフローや注意事項、判断基準などをまとめたものです。各業務のマニュアルを情報共有ツールに入力しておけば、従業員は必要な時にマニュアルを確認できます。
マニュアル作成は情報共有の代表的な手段のひとつであり、多くのツールに機能として取り入れられています。
2.チャット機能
情報共有ツールによく搭載されているのが、チャット機能です。チャット機能があれば、直接聞いたりメールをしたりするよりも効率的に相手とのやり取りができ、その内容をデータとして残せます。
情報共有ツールの中には、チャット専用のものも、一機能としてチャット機能を搭載しているものも存在し、コミュニケーションツールとして利用されています。
3.ファイル、スケジュール共有管理機能
ファイルやスケジュールの共有管理機能も、情報共有ツールによくある機能のひとつです。各種ファイルや個々のスケジュールを、わざわざメール添付したり報告したりせずに、ツールから共有することができるため、効率的な業務遂行に役立ちます。ファイルを同時編集できるケースも多く、これも業務の効率アップに繋がります。
4.翻訳機能
情報共有ツールには、入力した情報を翻訳できる機能を持ったものも登場しています。対応言語はツールによって異なりますが、翻訳機能があることで国内外における情報共有が叶うのが大きな魅力です。海外工場にマニュアルを共有することが可能になったり、海外との情報共有により新しいアイディアが生まれたりと、翻訳機能付き情報共有ツールは、特にグローバルな取り組みを目指す企業に重宝されています。
ツールを選ぶ時のポイント
情報共有ツールを企業の利益に繋げられるかどうかは、ツール選びに左右されます。そこで、情報共有ツールを選ぶ時に気をつけたい3つのポイントについてご説明します。
ポイント1.課題を解決できる機能があるか
情報共有ツール選定にあたっては、まず自社の課題を洗い出す必要があります。「どのような課題を情報共有によって解決したいのか」「課題解決のためにはどのような機能が必要か」を明確にした上で、自社の課題解決にマッチした機能を持つツールを見極めましょう。
情報共有ツールには、単一機能のものも複数機能のものも存在するため、どちらを取り入れるべきかも慎重に検討する必要があります。
ポイント2.ツールの使いやすさ
課題解決にマッチした機能があるからといって、すぐに導入する情報共有ツールを決めてはいけません。情報共有ツールを導入しても、機能が使いにくいものであれば、そのツールは活用されなくなってしまいます。
ツール選定においては、まずお試し版で使い心地を確かめるなどし、操作が複雑であったり使い心地が悪かったりするものは選ばないようにしましょう。
ポイント3.コストは予算に見合っているか
情報共有ツールは、長期にわたって活用していくものです。そのため、機能面だけでなく、コスト面の調整も重要になります。情報共有ツールの中にはユーザー数によって料金が異なるものも、無料のものも、オプションによって料金が変わるものも存在し、その相場はさまざまです。
情報共有ツール導入の際には、コストは予算に合っているか、より低価格・高サービスのツールはないか、よく検討するようにしましょう。
おすすめ情報共有ツール
ここからは、実際にリリースされているおすすめの情報共有ツールを5種ご紹介しましょう。
おすすめ情報ツール
ノートツール|Googleドキュメント

GoogleドキュメントはGoogleアカウントさえあれば誰でも無料で作成・閲覧可能なメモ共有ツールです。エクセルやワードと使い方が非常に似ているため、すぐに活用出来るでしょう。
スマホ・タブレット・パソコンなど多くのデバイスで利用可能なので、どこにいてもドキュメントにアクセスしてメモの共有が出来ます。さらに自動保存機能が用意されていることから「保存」をしなくても最新の状態を記録し、変更履歴も作成されます。
有料のビジネスプランでは、より強固なセキュリティと高性能な検索機能が用意されています。
【Google ドキュメントの料金プラン】
・パーソナル:無料
個人での利用に最適なプラン
・Business Standard:月額 ¥1,360 / ユーザー
ビジネス向けプラン。Google ドキュメントは Google Workspace に含まれています。
ノートーツール|Notion

Notionはドキュメントや表計算、プロジェクト管理など、多くの機能が利用できるメモ共有ツールです。各種マニュアルや議事録、タスク管理など、チーム内のあらゆる面での情報共有に利用できます。
業務に合わせて多数のテンプレートが公開されているため、多機能であっても簡単に使い始められる点も特徴です。
料金プランは無料プランと3種類の有料プランが用意されており、チームプランは無料トライアルが利用できます。
【Notionの料金プラン】
・パーソナル:無料
個人向け・5人のゲストと共有可能・ファイルアップロード5MBまで
・パーソナルPro:$4 / 月額(年間一括払い)、$5 / 月額(月々払い)
無制限のゲストと共有可能・ファイルアップロード無制限・30日間のバージョン履歴
・チーム:$8 / 月額(年間一括払い)、$10 / 月額(月々払い)
無制限のチームメンバー・同時編集可能・共有許可・管理者向け機能
・エンタープライズ:要見積
SAML SSO・SCIM・監査ログ・高度なセキュリティ設定
マニュアル・ノートツール|toaster team トースターチーム
社員・スタッフの知識・経験を見える化・仕組み化し、社内のあらゆる業務に関する情報をクラウドで一括管理できるクラウドサービス。誰でも簡単にマニュアル作成・共有が行え、作成したマニュアルをボタンひとつでタスク化できるのも特徴です。またノート機能を利用することでチーム全員でメモ・ノートを作成、共有することができます。
画像や動画、外部コンテンツとの連携に対応しており、柔軟なドキュメント作成ができます。また、共同編集機能や用語集機能、グループ作成機能なども搭載されていて使いやすく、セキュリティに重きが置かれているのも特徴です。
【toaster teamの料金プラン】
14日間無料トライアルを提供
・ライトプラン/月額35,000円(50名分のアカウント)
マニュアルがない、定着していない会社様におすすめのプラン
・ スタンダードプラン/月額60,000円(100名分のアカウント)
効率的な社員教育・アルバイトの積極採用の会社様におすすめのプラン
・ビジネスプラン/月額120,000円
大規模・多店舗展開・外国人採用に積極的な会社様におすすめのプラン
ノートツール|Dropbox Paper

Dropbox Paperは、データの保存・共有のためにある従来のDropboxに、作成機能が追加されたメモ共有アプリです。アプリだけでなくブラウザ版も用意されているため、さまざまなデバイスで使用が可能でしょう。
動画やGoogleマップの挿入が出来るため、精度の高いメモが簡単に作成出来ます。コメント機能には通常のコメント以外にも「対応済」「未対応」のステータスの選択が可能なので、多くのメモを確認する必要がある環境でも利用しやすいメモ共有アプリです。
【Dropbox Paperの料金プラン】
DropboxPaper はDropboxの機能のひとつのため、Dropboxの契約が必要です
・無料プラン:月額 0円/ユーザー
・plus 個人向け:月額 1,500円 / ユーザー
・Standard 成長中のチーム向け:月額 1,800円 / ユーザー
・Advance 複雑なチーム向け:月額 ¥2,880円 / ユーザー
ノートツール|Confluence

Confluenceはチームの情報共有やプロジェクト管理が可能なメモ共有ツールです。
作成したドキュメントを階層構造で整理できたり、ラベルを付けて管理できたりと、すぐに必要な情報にアクセスできます。そのほかにも用途別のテンプレートやSlack、Google Driveといった外部ツールとの連携機能など、簡単かつスムーズに情報共有を実現する機能が備わっています。
料金は無料プランと3種類の有料プランが提供されており、有料プランは無料トライアルが利用できます。
【Confluenceの料金プラン】
・Free:無料
10ユーザーまで・2GBのファイルストレージ
・Standard:¥660 / ユーザー / 月額
35,000ユーザーまで・250GBのファイルストレージ・
・Premium:¥1,250 / ユーザー / 月額
35,000ユーザーまで・無制限のファイルストレージ・管理機能・セキュリティ機能
・Enterprise:要見積もり
35,000ユーザーまで・無制限のファイルストレージ・管理機能・セキュリティ機能・サイト数無制限
ノートツール|Scrapbox

Scrapboxは共有性の高さが特徴のメモ共有ツールです。ページ内の単語をリンク化することで、欲しい情報にすぐにアクセスできます。複数ユーザーによる同時編集や、画像・動画等の添付にも対応しており、業務マニュアルや日報、雑記など、様々な用途で活用可能です。
SSL暗号化通信による情報保護や、SSO認証など、企業で利用する際にも安心なセキュリティである点もポイントです。
Scrapboxでは2種類の無料プランと、ビジネス向けに2つの有料プランが提供されています。
【Scrapboxの料金プラン】
・PUBLIC PROJECTS ARE FREE:無料
誰でも内容を閲覧できる「公開プロジェクト」を利用できるプラン
・PERSONAL / EDUCATION:無料
個人や非営利での利用に限定したプラン
・BUSINESS:¥1,100 / 月額 / ユーザー
ビジネス向けプラン。100ページまでは無料で試用可能。
・ENTERPRISE:要見積
大企業向けプラン。自社環境および独立したクラウド環境での利用が可能。
ノートツール|esa

esaはチームで情報を整理することをコンセプトに開発されたメモ共有ツールです。情報を共有する際に、ついつい完璧に情報を整理しようとしてしまって、いつまでたっても公開できない、といった悩みは珍しくありません。
esaではこうした課題を解決するWIP(書き途中)というステータスが設定できるのが特徴です。まずは気軽に途中段階のものをチームへ共有して、チームで情報を「育てる」という発想で設計されています。
料金プランは1ユーザーあたり月額500円のシンプルなプランとなっています。チーム作成月から2ヶ月後の月末までは無料トライアルとして料金が発生しないので、気軽に試してみることも可能です。
ノートツール|Qiita Team

Qiita Teamはエンジニア向けのコミュニティサービス「Qiita」を提供するQiita株式会社から提供されているメモ共有ツールです。エンジニアだけでなく、社内全体での情報共有やナレッジの蓄積を簡単に実現できます。
作成した情報に対して絵文字やコメントでフィードバック・リアクションが可能なため、コミュニケーションの活性化にもつながります。
Qiita Teamではメンバー数に応じた6つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。
【Qiita Teamの料金プラン】
・Personal:¥500 / 月額
メンバー上限1人の個人向けプラン
・Micro:¥1,520 / 月額
メンバー上限3人
・Small:¥4,900 / 月額
メンバー上限7人
・Medium:¥7,050 / 月額
メンバー上限10人
・Large:¥15,300 / 月額
メンバー上限17人
・Extra:¥15,300 / 月額
メンバー上限17人以上(18人目以降は月額720円 / 人が追加で発生)
IPアドレス制限、請求書払いに対応
ノートツール|DocBase

DocBaseは社内での情報共有をスムーズにするメモ共有ツールです。同時編集やMarkdown対応の使いやすいエディタに加え、テレワークにも対応する各種機能が用意されており、日報や議事録、マニュアル、企画書など、社内の様々な場面で利用可能です。
シングルサインオンや2段階認証、操作履歴の保存といったセキュリティを高める機能もあるため、企業での利用においても安心して利用できます。
DocBaseではメンバー数に応じた5つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。
【DocBaseの料金プラン】
・スターター:¥990 / 月額
ユーザー数上限3人・ストレージ3GB
・ベーシック:¥4,950 / 月額
ユーザー数上限10人・ストレージ10GB
・レギュラー:¥9,900 / 月額
ユーザー数上限30人・ストレージ30GB
・ビジネス100:¥21,450 / 月額
ユーザー数上限100人・ストレージ100GB
・ビジネス200以上:ユーザー数に応じて変動
ノートツール|NotePM

NotePMは社内のナレッジを蓄積するためのメモ共有ツールです。Web上で簡単にマニュアルなどのドキュメントを作成して共有できます。ツール内で画像の編集も可能なため、操作画面など、画像に説明を書き込んで説明するマニュアルなども簡単につくれるほか、動画を貼り付けて共有することも可能です。
本文だけでなく、WordやExel、PoperPoint、PDFなどのファイルの中身も全文検索できるため、必要な情報にすぐにアクセスできるのも特徴の1つです。
NotePMではメンバー数に応じた6つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。なお、閲覧のみであればユーザー数の3倍までの人数は無料で利用できます。
【NotePMの料金プラン】
・プラン8:¥4,800 / 月額
ユーザー数上限8人・ストレージ80GB
・プラン15:¥9,000 / 月額
ユーザー数上限15人・ストレージ150GB
・プラン25:¥15,000 / 月額
ユーザー数上限25人・ストレージ250GB
・プラン50:¥30,000 / 月額
ユーザー数上限50人・ストレージ500GB
・プラン100:¥60,000 / 月額
ユーザー数上限100人・ストレージ1TB
・プラン200以上:ユーザー数に応じて変動
ノートツール| Stock

Stockはシンプルな操作と機能で、IT知識のない人でも簡単にチームの情報を残すことができるメモ共有ツールです。情報のストックだけでなく、タスク管理やメッセージの送受信ができ、チームの情報共有やナレッジの蓄積が可能となります。
シンプルな機能であるものの、SlackやEvernote、メール転送など外部連携の機能や、バックアップデータの保持、誤削除防止など、チームでの利用に便利な機能は搭載されているため、簡単かつ便利に利用できます。
Stockは無料プランに加えて、標準機能のビジネスプランが4つと管理・セキュリティを強化できるエンタープライズプラン4つの系9プランが提供されています。
エンタープライズプランではアクセスログやデータエクスポート、IPアドレス制限、SSOなどより管理やセキュリティを強化できる機能が用意されています。また、銀行振り込みへも対応している点もポイントです。
【Stockの料金プラン】
・フリープラン:無料
ノート数累計20ノートまで・メンバー数無制限・ストレージ1GB
<ビジネスプラン>
・ビジネス5:¥2,480 / 月額(年間一括払い)、¥2,980 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数5人まで・ストレージ30GBまで・誤削除防止機能・2段階認証
・ビジネス10:¥4,980 / 月額(年間一括払い)、¥5,980 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数10人まで・ストレージ80GBまで・誤削除防止機能・2段階認証
・ビジネス20:¥9,800 / 月額(年間一括払い)、¥11,800 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数20人まで・ストレージ150GBまで・誤削除防止機能・2段階認証
・ビジネス30以上:ユーザー数に応じて変動
<エンタープライズプラン>
・エンタープライズ5:¥4,800 / 月額(年間一括払い)、¥5,800 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数5人まで・ストレージ100GBまで・誤削除防止機能・2段階認証・アクセスログ・SSO・銀行振込・専任サポート
・エンタープライズ10:¥9,800 / 月額(年間一括払い)、¥11,800 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数10人まで・ストレージ200GBまで・誤削除防止機能・2段階認証・アクセスログ・SSO・銀行振込・専任サポート
・エンタープライズ20:¥19,800 / 月額(年間一括払い)、¥22,800 / 月額(月々払い)
ノート数無制限・メンバー数10人まで・ストレージ400GBまで・誤削除防止機能・2段階認証・アクセスログ・SSO・銀行振込・専任サポート
・エンタープライズ30以上:ユーザー数に応じて変動
FAQツール|Qast

Qastは個人のノウハウやナレッジを蓄積することを目的としたメモ共有ツールです。簡単なUIで誰でもノウハウをドキュメント化して投稿できるだけでなく、社内版の知恵袋として質問を投げかける機能もあります。
作成したドキュメントはフォルダごとに整理をしたり、タグを付けて管理したりできるため、いつでも必要な情報をすぐに探し出せます。検索機能も高精度なため、添付ファイル内の文言を検索することも可能です。外部ツールとの連携機能を使えばメールやチャットツールで通知することもできるため、投稿を見逃す可能性を減らせます。
料金体系は月額費用に加えて初期費用が発生します。プランは2種類の有料プランが提供されています。
【Qastの料金プラン】
・スタンダードプラン
ユーザー数:20人〜・1ファイル容量50MBまで・Slack,Teams連携利用可能
・エンタープライズプラン
ユーザー数:20人〜・1ファイル容量250MBまで・Slack,Teams連携利用可能・IPアドレス制限・シングルサインオン・ダッシュボード
マニュアルツール|Teachme Biz

Teachme Bizはマニュアル作成に特化した情報共有ツールです。使用するツールに合わせてテキストや画像を表示するため、視覚的にわかりやすいマニュアル整備が叶う他、追加されたトレーニング機能は人材育成にも役立ちます。
また、ダイレクト翻訳機能を利用すれば、最短1時間で質の高い翻訳マニュアルが納品されるのも特徴で、グローバルビジネスにもおすすめです。
| スターター | 5万円(月額) |
| ベーシック | 10万円(月額) |
| エンタープライズ | 30万円(月額) |
※別途初期費用あり
チャットツール|Chatwork

Chatworkは、ビジネスチャットアプリの中でもよく利用されるツールです。個人単位でも組織単位でも利用が可能で、管理しやすいページ設定により、従業員同士、またクライアントと円滑にコミュニケーションを取ることができます。
低コストで導入が可能で、フリープランなら無料利用も可能です。
| フリー | 無料 |
| パーソナル | 400円(月額) |
| ビジネス | 500円(月額) |
| エンタープライズ | 800円(月額) |
コラボレーションツール|Google Workspace

Google Workspaceは、Googleが提供するグループウェアです。Gmailやチャット、ドライブ、ドキュメントなどGoogleの各種アプリケーションをデータ容量やセキュリティ、管理機能に特化した状態で利用できます。
Googleのアプリケーションは使い慣れている人が多いため、Google Workspaceはビジネス用の情報共有ツールとしても人気となっています。
| ビジネススターター | 680円(ユーザーあたりの月額) |
| ビジネススタンダード | 1,360円(ユーザーあたりの月額) |
| ビジネスプラス | 2,040円(ユーザーあたりの月額) |
| エンタープライズ | 要相談 |
まとめ
情報共有ツールについてご紹介しました。
情報共有は、これからの社会の中で企業価値を高め生き残っていくために、欠かせない手段のひとつです。導入時にはツール選定やノウハウの情報化など大きな労力が必要ですが、うまく導入ができれば、その後の業務は効率的になり、レベルアップしていくでしょう。
情報共有ツール導入の際には、ご紹介したポイントを参考にし、自社の課題に合ったシステムを慎重に選択するようにしましょう。
「toaster team トースターチーム」なら、業務手順書やマニュアル、業務プロセス、ワークフローを誰でも簡単に作成できます。社員・スタッフの知識・経験を見える化・仕組み化し、社内のあらゆる業務に関する情報をクラウドで一括管理できます。新人の即戦力化や業務の属人化の解消を通じて、組織の業務効率化と生産性向上につながるため、是非ご検討ください。