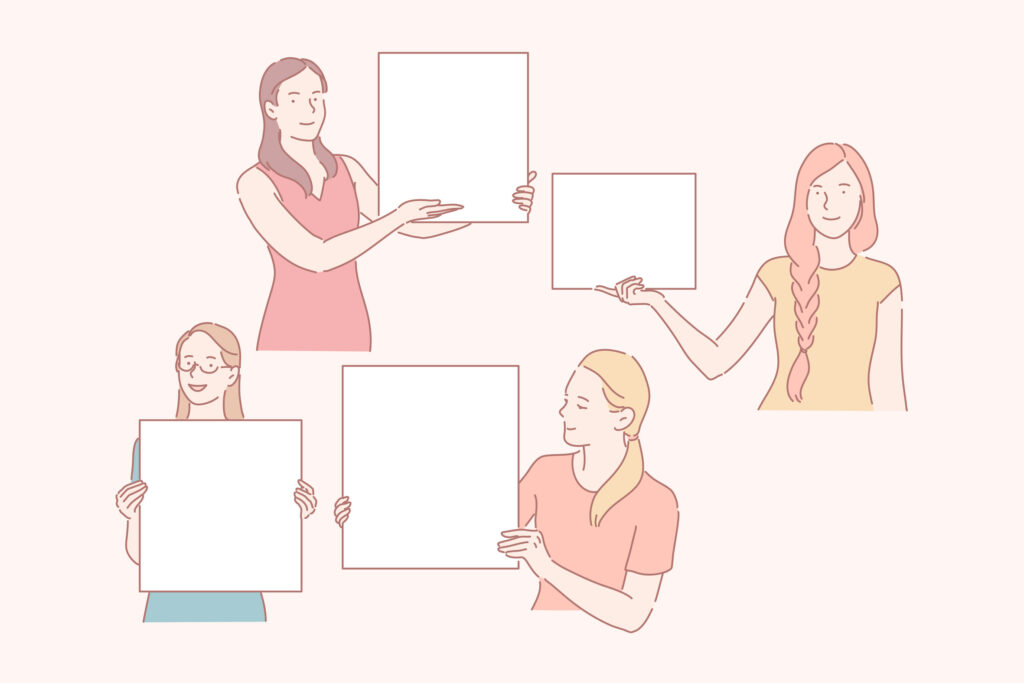これまでの仕事や取組みを見直して今後のアクションを決めるための、振り返りの手法の一つに「YWT」というものがあります。他に有名な手法に「KPT」という手法があります。
YWTとKPTは同じ「振り返りのための手法」でありながら明確な違いがあり、企業が得られる効果も変わるのです。この記事では、YWTとKPTの違いやYWTのやり方について説明しましょう。チームに最適な方法で業務の振り返りが出来るよう、ぜひこの記事を参考にしてください。
YWTとは
YWTとは日本で提唱された振り返りのフレームワークで「日本能率協会コンサルティング」が提唱しているものです。
Y「やったこと」・W「分かったこと」・T「次にやること」と、名称自体が日本語の頭文字をとっているため、その内容が分かりやすいでしょう。
YWTを行えば業務の振り返りが可能で、業務に対する取り組みの今後の継続可否や改善の必要性について知ることが出来るのです。
YWTのステップを繰り返すことで、組織は常に業務の振り返りが可能になり、良いものは継続し、問題点は改善するという流れが自然に定着します。
YWTの目的
YWTは業務の振り返りを行うためのものだとお伝えしましたが、多くの組織がYWTを行う目的とは何なのでしょうか?
その目的を理解した上でYWTに取り組みましょう。
1 課題を早期発見して客観的に整理する
YWTはメンバー全員が振り返りを行って情報を共有し、課題を早い段階で見つけるために実施されます。
文章にすることで業務を客観的に整理可能になるため、多角的に物事を考えられるようになるのです。また、YWTで振り返った内容を共有することで、情報の共有不足を原因としたトラブルも起こりにくくなるでしょう。
2 次に行うべきことを明確にする
当たり前のことですが業務をスムーズに進めるためには、業務に関係するメンバー全員が同じ方向を向いていなくてはいけません。
しかし、一部のメンバーのみが業務の進捗や問題などを把握し、他のメンバーはただ従っているだけという状態に陥っている組織が多いのも現実です。やる気を持っているメンバーであっても、次に行うことが分かりにくい状態では積極的に業務に携われません。
YWTを活用すれば、メンバー全員に次に行うべきことが周知されるため、そのような問題が起こりにくくなるでしょう。
3 コミュニケーションを活性化させる
YWTによって情報が共有されれば、メンバー同士で意見交換が盛んに実施されるようになります。
チームで一丸となって課題に向き合えるようになり、より良い改善点やアドバイスを見つけられるでしょう。コミュニケーションが活性化している組織は情報共有も進みやすく、業務の生産性・効率性を向上させることも出来ます。
YWTの具体的なやり方
ここからは、実際にYWTをどのように進めれば良いかを説明しましょう。
YWTは、テキストや書面に書き出して進めるもので、YWTの項目ごとに下記のようにまとめてメンバー内で共有します。
Y:やったこと
最初に、今までの取り組みの中で取り組んだことを書き出します。
なるべく主観を交えず、客観的な表現が出来るようにしてください。
もちろん良かった点だけでなく、問題点も書き出さなくてはいけません。
YWTは評価ではないことをメンバーもリーダーも理解するようにしてください。また、ルーチンワーク化しているものはYWTに載せてもあまり効果が得られないため、場合によっては省略しても良いでしょう。
W:分かったこと
次に「Y:やったこと」の内容を踏まえて、分かったこと・学んだことを書き出します。
あまり難しく考えずに「自分が考えたこと」と捉えて良いです。
実際に起こった事実だけを記載してしいまうと、「Y:やったこと」と同じ内容になってしまうため、事実の延長のような記載にならないように注意してください。
分かったことがなくては、最終ステップである「T:次にやること」に進めません。業務中にある問題が明確になった場合には、その原因について掘り下げると良いでしょう。
T:次にやること
「W:分かったこと」を、次回にどう活かしていくかをまとめます。
具体的には、良い点は継続を決め、問題点は改善案を考える作業です。
「Y:やったこと」「W:分かったこと」が共有出来ていれば、メンバー一人ひとりに改善策やアイデアがあるはずなので、その意見を積極的に取り入れましょう。
この流れで生まれた「T:次にやること」は、次回のYWTの「Y:やったこと」に当てはまります。つまり、YWTがこうやって繰り返されれば、その組織は常に業務の振り返りが出来るということです。
YWTとKPTの違い
冒頭でKPTとYWTは似ているとお伝えしましたが、実際には明確な違いがあります。
それぞれの違いを理解した上で、自社に最適な方法を導入するようにしてください。
まずKPTについての説明をすると、KPTとは「Keep:良かったこと・今後も継続したいこと」「Problem:改善したいこと・止めたいこと」「Try:改善策・アイデア・試したいこと」の頭文字を取っている言葉です。
YWTと同じように、次にやることを決めるための振り返りに使用される手法であるため、YWTとKPTの違いがよく分からないという方も多いようです。ここからは、YWTとKPTの違いを分かりやすく説明しましょう。
個人単位かチーム単位か
YWTとKPTはその単位がどこに置かれているかに違いがあります。
簡単に説明すると、KPTはチーム単位、YWTは個人単位で使用されることが多いのです。
ここからは、2つの違いをより細かくまとめましょう。
KPTは「チームの振り返り」のために行います。KPTの実施によりチームの問題点が洗い出され、今後チーム全体でどう改善していくかを考えるのです。
それに対してYWTは「個人の振り返り」のために行われるものです。自分が行ったことで何が分かり次にどう活かしていくのかを考え、個人が経験と学びを活かして成長するという部分に、重きが置かれています。
ただし、KPTを個人で、YWTをチームで使ってはいけないというルールはありません。上記はあくまで目安としてお考えください。
「T:次にやること」に向かうまでの方法が違う
YWTもKPT改善策などの次のアクションを明らかにするために行われますが、それぞれの思考の進め方に多少の違いがあります。
この記事でお伝えしたように、YWTはY→W→Tの一方通行で思考を進めるのに対し、KPTは実施した行動と解釈をつなぎ合わせた上で次に行うべき行動を明確にするのです。
KPTでは「K:良かったこと・今後も継続したいこと」「P:改善したいこと・止めたいこと」は同時に行っても、順番に行っても構いませんが、「K」と「P」の両方の内容から「T:改善策・アイデア・試したいこと」が決められます。
Y→W→Tの流れを重視するYWTとKPTはその流れにも違いがあると言えるでしょう。
まとめ
YWTの意味や方法、KPTとの違いについて説明いたしました。組織が業務を進める中で振り返りは欠かせない行為であり、振り返りが行われるからこそ、組織は成長出来るのです。この記事を参考に正しい方法でYWTを進めてください。また、YWTはチームで共有することでそのメリットが得られるものです。情報共有ツールなどを活用してリアルタイムでYWTでの振り返り内容の共有を行い、次にやるべきことをメンバー全員で理解できるような環境を構築しましょう。