営業活動をより効果的に、効率的に行う手段として、「セールスイネーブルメント」が注目されています。各企業ではセールスイネーブルメントツールの導入も進み、外部SFAやCRMなどとの連携による効果も期待されるようになりました。
そこで今回は、セールスイネーブルメントについて、概要や効果、実現のポイントなど詳しくご紹介します。
セールスイネーブルメントとは
セールスイネーブルメントとは、「営業の売上最大化のためのあらゆる取り組みを総括的に設計・管理する営業施策」のことです。今まで各部門に分けて行われてきた取り組みを、「営業売上を最大化するための一連の施策」として捉え、各部門が連携して設計や管理を行うことで、最適化を図ります。
例えば、これまでの企業体系においては、営業プロセスの把握は営業部門、マーケティングはマーケティング部門、ツールの導入・開発はシステム部門、営業人材の教育は人事部門といったように、行う取り組みによって部門分けがされ、業務や人材が分断されてきました。
しかし、営業プロセスの把握もマーケティングもツール導入も、そして営業人材の育成も、目的は同じで「営業の売上を最大化すること」です。
しかし、目的が同じ取り組みにも関わらず、業務や人材が分断されていては、それぞれの取り組みは目的に対して最大効果を生み出せません。
そこで生まれたのが、セールスイネーブルメントという考え方です。セールスイネーブルメントでは、「営業の売上を最大化する」取り組みを、部門分けするのではなく、一貫した営業プロセスとして考えます。そして、この営業プロセスを総括的に設計・数値化して管理することによって、取り組みの最適化や効率化を目指します。
セールスイネーブルメントが注目されている背景
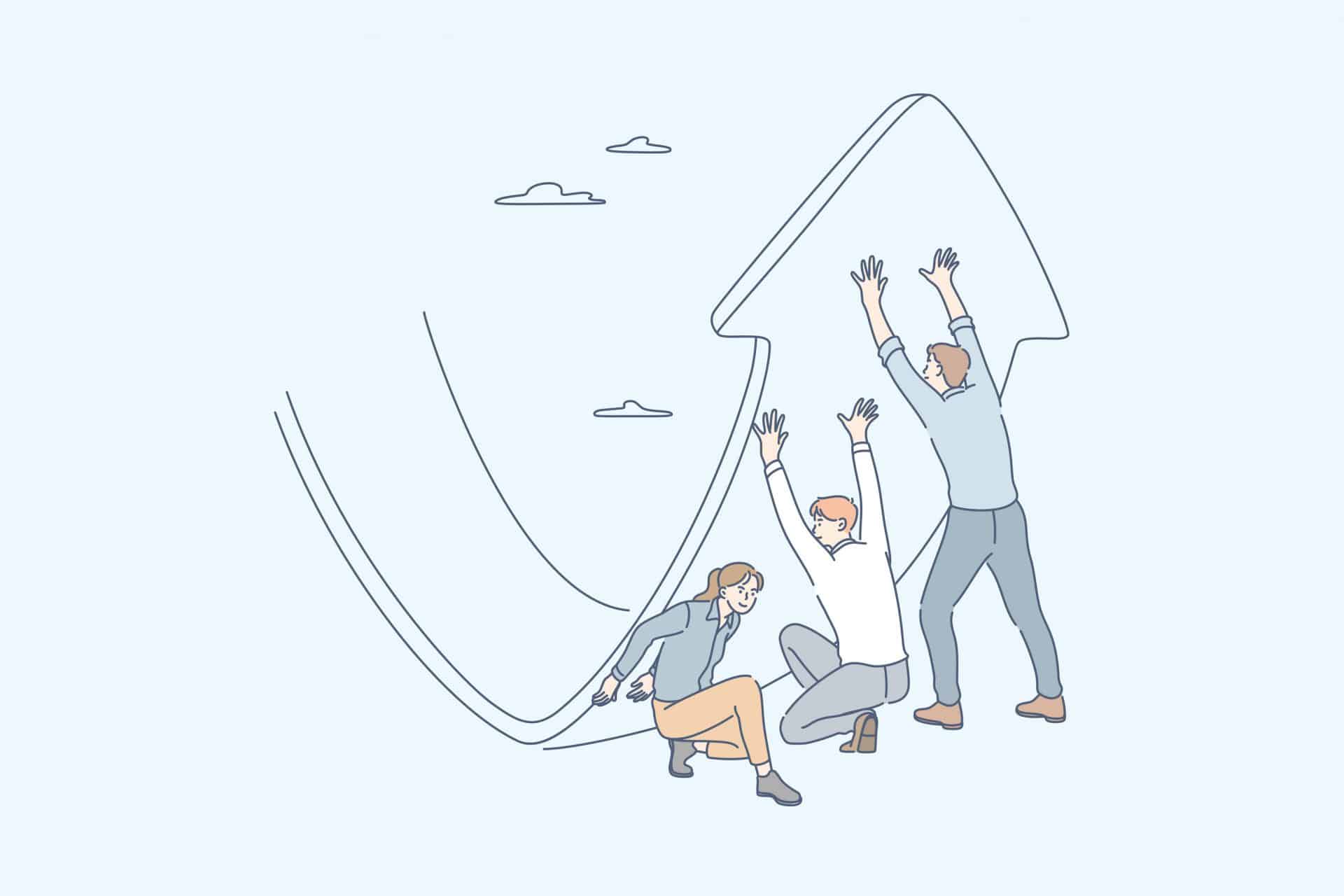
セールスイネーブルメントが注目されている背景には、多くの営業組織が抱える「カスタマーニーズの複雑化」「営業の属人化」という2つの問題があります。
背景1 カスタマーニーズの多様化
近年、顧客のニーズは多様化しています。ニーズの多様化に伴いマーケティングの重要性は高まり、高度なマーケティングを自動で行うツール(マーケティングオートメーションツール)が多くの企業で活用されるようになりました。
ただし、せっかくマーケティング部門が優れた情報を提供しても、営業部門とマーケティング部門がうまく連携できていなければ、情報の効果的な活用は行えません。マーケティング部門からの膨大な情報を処理しきれず、見込み客を取りこぼしてしまうことも考えられます。
セールスイネーブルメントにより業務の連携をスムーズにすれば、効果的な人材育成やツール活用により、営業の効率化が図れ、情報を有効活用できる状況を整えやすくなります。そうすることで、多様化したカスタマーニーズに対応する営業も行いやすくなります。
背景2 営業の属人化
営業業務は個人的な活動が多く、属人化しやすい傾向にあります。そのため、営業部門独自の不明瞭な分析が行われていたり、非効率的で再現性の低い施策が実行されていることも少なくありません。
営業組織だけの限られた情報による営業活動では、営業成果の最大化は期待できないのです。
そこで、セールスイネーブルメントに基づき、マーケティングやシステム開発など、営業部門の枠を超えたあらゆる取り組みを、営業活動の強化・改善に向けてトータル設計すれば、各取り組みを総合的に管理し、効果を数値化することが可能になります。その情報を生かして、各取り組みを最適化することができます。
セールスイネーブルメントの効果

セールスイネーブルメントの効果および目的は、「営業活動の最適化・効率化」です。具体的には、以下のような効果が期待できます。
効果1 営業力の向上・平準化
営業は属人化しやすい業務です。しかし、セールスイネーブルメントによって営業プロセスをトータル設計すれば、営業の実情に合った人材育成やツール導入が可能です。営業スキルの底上げや営業の効率化を目指せます。
営業スキルの平準化も進めやすく、営業の属人化は改善し、結果、全体の営業力向上が期待できます。
効果2 各取り組みの貢献度を可視化
セールスイネーブルメントは、営業プロセスを分断せずにトータル設計し、各取り組みを数値化して管理します。
これにより、各取り組みの営業売上に対する貢献度が一目でわかるので、続けるべき取り組みや中止すべき取り組み、また次に行うべき取り組みの判断が、正確かつ迅速に行えるようになります。
効果3 顧客ニーズを的確に反映した営業
セールスイネーブルメントによってマーケティングと営業が深く繋がるようになれば、マーケティングによる情報を営業に反映しやすくなります。多様化・複雑化する顧客ニーズも的確に把握でき、効果的に営業施策へと繋げられます。
セールスイネーブルメントを実現するためのポイント

セールスイネーブルメントを実現するために重要な3つのポイントをご紹介します。
ポイント1 SFA・CRMツールを用いたデータ蓄積
セールスイネーブルメントを実現するには、あらゆるデータの蓄積が必要です。例えば、営業売上や受注率、顧客情報、人材育成プログラムの履歴などです。
このような情報は、SFAおよびCRMツールを用いることで効率的な蓄積と管理ができます。
またSFA・CRMによる営業スコアだけでなく、顧客アンケートによるスコアも取得すれば、データの厚みは増します。
※SFA:「営業支援システム」営業活動を支援し効率化するためのツール
※CRM:「顧客関係管理」既存顧客との継続的な良好関係を築いていくための経営手法・ツール
ポイント2 各取り組みの貢献度を把握しPDCAを回す
前章でも触れましたが、営業に対する各取り組みを数値化することは、セールスイネーブルメントの重要な要素です。SFAやCRMのデータをもとに数値化した情報によって、各取り組みの営業成果に対する貢献度を把握する必要があります。
それを元にPDCAサイクルを回すことで、継続的に各取り組みの最適化が進められます。
※PDCAサイクル:継続的な業務改善のためのフレームワーク(Plan計画、Do実行、Check測定、Action改善)
ポイント3 セールスイネーブルメントの専門部署を配置
セールスイネーブルメントを実現するためには、セールスイネーブルメントの専門部署を配置する必要があります。部門を分断しないのがセールスイネーブルメントの特徴でもあるため、各部門に担当者を置くよりも、全体を見る専門部署を置いた方が良いでしょう。
実際、海外では専門部署を置いてセールスイネーブルメントを進める企業が多いようです。
ポイント4 セールスイネーブルメントツールの活用
セールスイネーブルメントのための専用ツールを活用するのも、自社のセールスイネーブルメントを実現するのに効果的です。
セールスイネーブルメントツールを使えば、データの分析やコンテンツの管理、人材育成などセールスイネーブルメントに必要なことを、ツール上で実行することが可能になります。ツールによって一元的にセールスイネーブルメントのプロセスを管理することで、セールスイネーブルメントはより効率的に進められるでしょう。
セールスイネーブルメントの取り組み事例

ここからは、課題解決のためにツールを用いてセールスイネーブルメントに取り組んだ企業の事例を2つご紹介します。
A社の場合
ペイメント事業を手掛けるA社では、営業活動に関して以下のような課題を抱えていました。
・顧客のニーズがわからず、資料の的確なアップデートができない
・顧客の動向やニーズを可視化したい
このような課題は、マーケティング情報と営業活動がうまく連携できていない点に問題があると考えられます。
そこで、セールスイネーブルメントの必要性を感じ、セールスイネーブルメントツールの導入を決めました。ツールを活用することで顧客の資料閲覧データや営業成果が明確に把握できるようになりました。
また、そのデータと、ツールに連携したSFAデータを合わせて分析することで顧客ニーズに合った資料作りが可能になり、商品に興味を持つ顧客に対し、興味のある内容の資料を提示しながら、確率の高い営業アプローチができるようになりました。
B社の場合
IT系の事業を担うB社では、営業活動に以下のような課題を持っていまいした。
・営業担当が、自社サービスに興味のない顧客への電話業務を負担に感じていた
これらの課題を解決するため、B社はセールスイネーブルメントツールを導入しました。
ツール導入後には、「資料を読んだか」「どのページに興味を持ったか」など、自社サービスに対する顧客の温度感やニーズが事前に把握できるようになりました。
これにより、営業担当は顧客の温度感やニーズに合わせた事前準備とアプローチができるようになりました。また、可視化されたデータによって成功率の高い顧客へのアプローチを優先できるようになり、営業担当の負担軽減にもつながりました。
まとめ
セールスイネーブルメントは、多様化する顧客ニーズに対応し、営業成果を最大化させるために効果的な施策です。
会社のあらゆる部門の取り組みは、営業活動をバックアップするために行われていると考えれば、セールスイネーブルメントに基づいた営業体制は合理的であると言えるでしょう。
また、セールスイネーブルメントを実現するには、専用ツールの導入が有効です。専用ツールを活用すれば、セールスイネーブルメントの実現はスムーズになり、効果的なデータ分析や顧客へのアプローチが行えます。



